古代女性論と漢詩・唐詩・宋詩研究 kanbuniinkai紀 頌之
古代女性論のサイト
唐代の女性 6.. 服装と化粧7. 女性と結婚

漢文委員会 kanbun-iinkai 紀 頌之
漢文委員会の漢詩のサイト集
一覧表
1
| 漢詩総合サイト 7 |
漢文委員会kanbun-iinkai 紀頌之 |
| ジオ漢詩サイト |
漢文委員会kanbun-iinkai 紀頌之 |
| 漢詩総合サイト fc2 |
漢文委員会kanbun-iinkai 紀頌之 |
| 基本詩集・漢詩総合サイト |
漢文委員会kanbun-iinkai 紀頌之 |
5
| 漢詩と古代女性論のサイト |
漢文委員会kanbun-iinkai 紀頌之 |
6
| 漢詩と長安都市計画 |
宇宙の中心である皇都 |
漢文委員会kanbun-iinkai 紀頌之 |
7. 李白のサイト
8. 杜甫のサイト
9. 韓愈のサイト
10. 漢から六朝期の詩サイト
11. 隋・唐・宋の詩サイト
12. 女性詩サイト
13. 李商隠詩サイト
ブログ集
1. 李白全詩訳注解説ブログ
| 李白全集案内 http://blog.livedoor.jp/kanbuniinkai10/archives/68119974.html |
2. 韓愈全詩文訳注解説ブログ
| 韓愈全詩案内 http://blog.livedoor.jp/kanbuniinkai10-rihakujoseishi/archives/7131636.html |
3. 杜甫全詩訳注解説ブログ
| 杜甫全詩案内 http://blog.livedoor.jp/kanbuniinkai10-tohoshi/archives/68103138.html |
4. 特集詩 訳注解説ブログ
| 特集詩 訳注解説 http://kanbunkenkyuu010.blog.fc2.com/ |
5. 花間集・玉臺新詠・女性詩全詩
訳注解説ブログ
| 花間集案内 http://blog.livedoor.jp/kanbuniinkai10-godaisoui/archives/36850905.html |
6. 中國詩訳注解説と歴史ブログ
| 古代女性論ブログ http://kanbunkenkyu88.blog-rpg.com/ |
7. 漢詩・唐詩・宋詩と散歩ブログ
散歩ブログ (準備中) |
李白詩のサイト
http://kanbuniinkai12.dousetsu.com/
唐代の女性(Ⅰ)-03. 服装・化粧と結婚
| 唐代の女性 (Ⅰ) 目録 | |
1.唐の音楽と歌舞 2.唐の歌妓(妓優) |
|
02---------- 3.唐時代の気風 4.生活実態 5.食事と料理 |
|
03---------- 7.女性と結婚 |
|
04---------- /年中行事/運動・競技/屋外遊戯/酒と酒宴/屋内娯楽/喫茶と茶道/散楽と劇/牡丹の流行/異国趣味/無頼と刺青/遊侠と奢豪/虎と狐への信仰 9.女性の家庭内の娯楽と節句の行事には次のようなものがあった。 人日の剪彩/蕩鞦韆(ぶらんこ蕩ぎ)/闘百草(百草を闘わす遊び)/弓子団子/七夕の乞巧(針仕事の占い)/拜新月/蔵鈎(鈎隠し)/動物の飼育 元宵節観燈(燈龍の見物)/春薪踏青(ハイキング)/芝居見物/ポロ見物 |
|
閨意朱慶余
昨夜洞房停紅燭,待曉堂前拜舅姑;
妝罷低聲問夫婿,畫眉深淺入時無昨夜洞房紅燭を停む,待曉堂の前 舅姑に拜す;妝罷り 低き声にて夫壻に問う、画ける眉の深浅は 時に入【あ】うや無【いな】や。
朱慶余:中国,中唐の詩人。 ?中 (福建省) の人。名,可久。慶余は字。宝暦年間の進士で,秘書省校書郎にいたった。詩は清新な表現でこまやかな描写を得意とし,親交のあった張籍から高く評価された。
唐代の人々が美しいと感じる女性は、どのような人であったか。玄宗は太子の妃を選ぶ時、はっきりと「背が高くて色の白い」女子を選ぶようにと言ったことがある(『唐語林』巻一)。寧王李憲(容宗の長子)は、隣に住む餅売りの妻を見初めたが、それは彼女が「肌のきめが細かくて白く、目が輝いて美しい」からであった(『本草詩』情感)。これらは、およそ基本的に唐代の人々の女性についての審美観を反映しており、また中国古代の女性美についての一般的な標準とも一致している。つまり、「長、白、美」の三つであった。長とは身長が高いこと、白とは皮膚の色が白いこと、美とは容貌が美しいことである。中国古代の美人の基準は主にこうした点にあり、唐代の人々も例外ではなかった。その他に、「桜桃 焚素(自居易家の歌妓)の口、楊柳 小蛮(同じく歌妓)の腰」(白居易「楊柳枝詞」)というように、唐代の詩詞や著作の中に反復して出てくる、小さい口、細い腰、白い手、細い足などは、秀麗で繊細な美人の特徴であり、だいたい各時代のそれと一致している。
しかし、人々は唐代の女性美には他の時代にはない特色があったことに注目している。唐代の男性は、背が高く色が白く、細くて優雅な女性を好んだが、しかし決して林黛玉(『紅楼夢』の主人公)のような病弱なものは喜ばなかった。彼らは健康で雄々しく、はては豊満でぽっちゃりした美人を大いに尊んだ(これはただこの時代の好みというだけであって、決してあらゆる人々がいつもこうだったわけではない)。この点に関しては、証拠はたいへん多く、すでに人々の周知のことである。
唐代の絵画、彫像に出てくる女性の姿を見ると、彼女たちはみな確かに顔は満月のようにふくよかであり、からだは豊満でまるまるとしている。そして、あの軍服を着て馬に乗って弓を引く女性は、特に堂々とした勇敢な姿を示しており、痩せて弱々しい姿はほとんど見られない。これはまさに唐代の人々の審美観と現実の生活そのものの反映であった。唐代第一の美人楊玉環(楊貴妃)は豊満型の美人であり、漢代の痩身型の美人趨飛燕と並んで、「燕は痩せ環は肥え」といわれ、美人の二つの典型と称された。
このような美意識は、唐代の社会生活と社会の気風から生れた。というのは、唐代の物質生活は比較的豊かであったから、身体がふっくらとした女性が多くいたのである。また社会の気風は開放的であり、北朝の尚武の遺風を受け継ぎ、女性は家から出て活動することもわりに多く、また常に馬に乗って矢を射る活動にも加わっていた。それで、往々女性は健康的で楓爽たる姿をしていたのである。こうした現実が人々の審美観に影響し、そしてこの審美観と時代の好みとが、逆に女性たちにこの種の美しさを極力追求させたのである。少なくとも「楚王、細き腰を好む」ために、食を減らすといったことはなかった。これによって、女性は健康で雄々しくかつ豊満であるといった傾向が助長されたのである。
* 『筍子』等に、昔、楚の霊王は腰の細い美人を好んだ。それで宮中の女性は食を減らし餓死したという故事がある。
審美観と密接な関係がある服装と化粧は、女性の生活の重要な一部分であった。この方面の論文や著書はたいへん多いが、ここでは、すでに発表された著作のうち、主として孫機先生の「唐代婦女の服装と化粧」(『文物』一九八四年第四期)と題する一文によって簡単に紹介し、その後で、唐代女性の服装と化粧について、少しばかり私の意見を述べようと思う。
唐代の女性の服装は、貴賎上下の区別なく、だいたいにおいで杉(一重の上着)、裾(スカート)、岐(肩かけ)の三つからなっていた。上着の杉のすそは腰のあたりで裾でとめる。裾はたいていだぶだぶとして大きく、長くて地面をひきずるほどであり、普通六幅(一幅は二尺二寸)の布で作られた。肩に布をかけるが、これを「被服」といい、腰のあたりまでゆったりと垂れている。また、常に杉の上に「半背」(袖の短い上着)をはおったが、これはかなり質のよい布で作り、主に装飾のためのものであった。足には靴か草履をはいたが、これらは綿布、麻、錦南、蒲などで作られていた。
唐代の女性は、化粧にたいへん気をつかった。普通は、顔、肘、手、唇などに白粉や頬紅をつけ、また肌を白くし、あるいは艶やかにしたが、それ以外に眉を画くことをことのほか重視した。眉毛の画き方はたいへん多く、玄宗は画工に「十眉図」を描かせたことがあり、それらには横雲とか斜月などという美しい名称がつけられていた(『粧楼記』)。ある人は、唐代の女性は眉毛の装飾に凝り、それはいまだかつてなかった水準に達したと述べている。その他、彼女たちは額の上に黄色の粉を塗り、それを「額黄」といった。また、金箔や色紙を花模様に切り抜いて両眉の間に貼るのが流行り、「花細」、「花子」などと呼ばれた。その他、両頬に赤、黄の斑点、あるいは月や銭の図柄を貼るケースもあり、これは「粧暦」壷はえくぼの意)といった。
髪型はさらに豊富多彩で、段成式の著作『誓贅晶』 には、多種多様の髪型が列挙されている。たとえば、半翻誓、反棺誓、楽訪誓、双環望仙誓、回鶴撃、愁来誓、帰順誓、倭堕撃など。撃の上に、色々な宝石や花飾りの鉄を挿したり、歩揺(歩く度に美しく揺れ光る髪飾り)を着けたり、櫛を挿したりして飾った。それらは、貧富や貴賎によって定まっていた。
衣服、装飾などはきわめて墳末な物ではあるが、かえって一滴の水と同じょうに、往々にして社会の多種多様の情況をよく映し出すことができた。唐代の女性の服飾もその例に漏れない。そこに浮かび上がる特色もまた、まさに唐代という社会の諸相を映し出す映像そのものであった。
一 胡 装
胡服を着て胡帽を被る ー 「女が胡の婦と為り胡敏を学ぶ」(元横「法曲」)、これは唐代女性の特別の好みの一つであった。唐代の前期には、女性が馬に乗って外出する際に被った「帯解」(頭から全身をおおうスカーフ)は、「戎夷」(周辺の蛮族)から伝わった服装であった。また、彼女たちは袖が細く身体にぴったりした、左襟を折り返した胡服を好んで着た。盛唐時代(開元?大暦の間)には、馬に乗る時に胡帽をかぶるのが一時流行した。胡服・胡帽の姿は絵画や彫刻、塑像の中で、随所に見ることができる。
彼女たちは、また胡人の化粧をも学んだ。
時世妝
作者:白居易李夫人→
文章還沒有進行過校對和格式化,或文章還不全,不能保證任何部分可靠。
警戒也。
本作品收?於:《新樂府》
時世妝,時世妝,出自城中傳四方。
時世流行無遠近,腮不施朱面無粉。
烏膏注唇唇似泥,雙眉畫作八字低。
妍?黑白失本態,妝成盡似含悲啼。
圓鬟無鬢堆髻樣,斜紅不暈赭面?。
昔聞被發伊川中,辛有見之知有戎。
元和妝梳君記取,髻堆面赭非華風。
ファッション
時世赦 白居易
時世赦 時世赦、
城中自り出でて四方に伝わる。
時世の流行 遠近無く、
額は朱を施さず面に粉無し。
烏膏を唇に注して唇は泥に似、
双眉を画きて八字の低ると作す。
研寅(美醜) 黒白 本態を失い、
赦成れば尽く含悲噂に似たり。
円贅は贅無く椎誓(蛮人のまげ)の様、
斜紅は尊さず描面(蛮人の化粧)の状。
元和(八〇六-八二〇年)の赦琉(顔の化粧、髪型) 君 記取よ、
警椎、面緒は華風に非ざるを。
このように、白居易は中国風でない化粧や髪型の流行を慨嘆している。こうした胡服や胡粧は大半が北方と西北の遊牧系少数民族から伝わってきた。服装と装飾が胡族化したことは、まさに強盛な大帝国が率先して外来文化を吸収したことを、最も良く示す現象である。
唐代の人々には、宋代の人のような「〔中華の〕遺民 涙尽く 胡塵の裏」(陸訪「秋夜将に暁に離門を出で涼を迎えんとして感有り」)といった亡国の痛みはなかったので、当然にも胡服や胡柾によって中華の中心たる中原が胡化するとか、生臭い土地に変り「蛮夷」 の邦になるといった恐れや心配は全く頭に浮かばなかった。ただ唐の中期になり、「胡騎 煙塵を起こす」というようになると、始めて「女が胡の婦と為り胡敏を学ぶ」(元横「法曲」)のは乱国の兆であると、悲しみ嘆く人が出てきた。国勢が衰退したので、統治者の自信が揺らいだのである。魯迅は、「誰か女性の服装を慨嘆して不満を述べる人が出てくれば、われわれはその時代の支配階級の状況がたいていうまくいっていないことを知る」と、三一日で本質を喝破している(魯迅「女性に関して」)。
二 戎装と男装
唐代の女性、とりわけ宮廷の女性は、常に戎装(軍装)と男装を美しいものと考えていた。高宗の時代、太平公主は武官の服装をして宮中で歌舞を演じたことがある。また、武宗の時代、王才人は武宗と同じ服を着て一緒に馬を駆って狩りをした。それで天子に上奏する人はいつもどちらが天子か見まちがったが、武宗はそれを面白がった。宮女たちが軍服を着たり、男装するのは全く普通のことだった。「軍装の宮妓、蛾を掃くこと浅し」(李賀「河南府試十二月楽詞」)、「男子の衣を着て靴をはく者がいる。あたかも実、契丹の服のようである」(『新唐書』車服志)などの記録はたいへん多い。絵画や彫像の中にはさらに多くの戎装、男装の宮女の姿を見ることができる。こうした風潮は民間にも伝わり、妓女や俳優(役者)たちも常に「装束 男児に似たり」(李廓「長安少年行」)といわれ、また「士流(士人階級)の妻は、あるいは大夫の服を着、あるいはまた男物の靴、杉(上着)、鞭、帽子などを用いて、妻も夫も身仕度が同じだった」(『大唐新語』巻一〇)といわれている。男女が同じ服を着て、妻と夫の区別も無いとは、本当に平等な感じがする。こうした風潮が生れたのは、社会の開放性と尚武の気風があったからにはかならない。当時の若干の保守的な人々は、男女の服装に違いがなく、陰陽が逆さまになっている情況に頭を横に振りながら、「婦人が夫の姿になり、夫は妻の飾りとなっている。世の中の顛例でこれより甚だしいものはない」(『全唐文』巻三一五、李華「外孫雀氏二該に与うる書」)と慨嘆した。これぞまさしく、女性が男装する風潮は封建道徳の緩みであると説明する直接的表現ではないか。
346
三 時世粧
唐代の三百年間には、服装、装飾は何度も変化し、各時代にその時代の時世粧があった。「時世赦 時世赦、城中自り出でて四方に伝わる」、「小頭鞋履 窄衣裳……天宝末年の時世赦」(自居易「時世赦」、「上陽白髪人」)などと詩に書かれている。唐代の女性はファッションに大変に凝った。彼女たちはモダンなもの、新奇なものを追うのが大好きで、しばしば宮中から何か新しいファッションが伝わってくると、民間も競ってそれをまねたので、すぐ社会全体の流行になった。沈従文先生の『中国古代服飾研究』、孫機先生の「唐代婦女の服装と化粧」等の著作は、唐の各時期の女性の服装や髪型などの変化を列挙している。たとえば、唐初の杉と裾は窄くて小さいが、盛唐時代になるとゆったりと大きいものに変わり、中庸以後になるとますます幅の広い大きなものになり、ついに節約を唱える皇帝が出てきて女性の服装に干渉せざるを得ないことにまでなってしまった。また、たとえば、あまり目立たない眉毛にしても、その色や形は時々変わり、「一日新たに妝えば 旧き様を?ち、六宮 争って画く 黒煙の?」(徐凝「宮中曲」)という情況となった。新式のモードが登場するたびに、旧式のものは人々から投げ捨てられて時代遅れとなった。花嫁は「妝罷り 低き声にて夫壻に問う、画ける眉の深浅は 時に入【あ】うや無【いな】や。」(朱慶余「近ごろ試みに張籍水部に上る」)、と尋ねるのも無理もないことであった。服装の変化のリズムは非常に速く、女性は目新しいモードを追いかけるのが大好きで、服装が流行に合っているかどうかを気にかけたが、それは何を意味していたのだろうか。人々は次のように言うかもしれない。どうせただ悠々と満ちたりた生活を送っていた貴婦人たちの、賛沢で退屈しのぎの表れであり、また妃嬢・姫妾・娼妓など色気で寵愛を求める者の、男を龍絡する手段にすぎないと。こういう説明は確かに誤りではない。しかし、別の角度から見れば、社会に新鮮な活力がみなぎっていた一つの表現であるとは言えまいか。何十年、何百年も服装が相も変わらず変化しなかったならば、それは人類の悲劇でしかないであろうし、また、その社会が硬直化し停滞し、気息奄奄となっている表れであると言えるのではないだろうか。
四 身体を露出するファッション
唐初、女性が騎馬で外出する時には、冪籬を着用して頭から全身を蔽っていた。後世になると、冪籬の代りに帷帽(山高帽のつばの左右と後部に首を隠す網が垂れているもの)をかぶった。帷帽から垂れている網は首まで覆うだけで、もう全身を覆うものではない。盛唐の開元年間に至ると、女性は騎馬で外出する時にはただ胡帽をかぶるだけで、顔も、甚だしい場合には頭髪さえも外に露出していた。
唐代の女性の服装は、まさに社会の風気が開放的になるに従って自由となり、益々拘束がなくなっていったのである。家庭での服装については、私たちは唐代の絵画の中に見ることができる。たとえば、有名な永泰公主の墓の壁画の中に見られる女性などは、たいてい上着も下着も太めにゆったり美しいが、しかし胸も乳も露わにされている。このような露出的な服装は、現代の人々さえ驚かせずにはおかないが、また、こうした服装が人々に与える優美さに賛嘆の声を上げざるを得ないのである。
永泰公主の墓の壁画
人々はしばしば次のように言う。肌を露わにするのは支配階級の腐敗し、酒色に溺れた生活の反映であり、頭廃の風俗であると。しかし実際は、女性の服装が最も束縛されていた封建末期においでも、あるいは女性がほとんど全身を隠しているイスラム教支配地域においても、支配階級は同じく荒淫の生活を送っていたのであり、ただ恥部を隠す布を何枚か増やして、なお一層虚偽をふくらませたに過ぎない。筆者はむしろ次のように感じる。こうした女性の服装は、唐代の社会の開放的な風潮と女性が封建道徳の束縛を少ししか受けなかったことの表れである、あるいはまた、唐代の人々が人体の自然の美しさに目を向けた美意識の進歩の表れである、と。
宮中曲二首 作者:徐凝 唐 《全唐詩卷474》一、
披香侍宴插山花,厭著龍銷著越紗。
恃賴傾城人不及,檀妝唯約數條霞。
二、
身輕入寵盡忌私,腰細偏能舞柘枝。
一日新妝拗舊様,六宮爭畫黑煙眉。
【女四書】
① 辻原元甫つじはらもとすけが編した女性向けの訓戒書。七巻。1656年刊。「女誡じよかい」(後漢の曹大家著)、「女孝経」(唐の陳?ちんばくの妻、鄭てい氏著)、「女論語」(唐の宋若?そうじやくしん著)、「内訓」(明の永楽帝の仁孝文皇后著)の四書を集めて、和訳したもの。
② 中国、清の康熙こうき年間に王相おうしようが編纂した女子のための教訓書。四巻。「女誡」「女論語」「内訓」に、自分の母、劉りゆう氏著「女範」を加えて注をつけたもの。江戸末期に西坂天錫てんしやくが和訳。
服飾と化粧
長い戦乱のため、乱れていた冠服制度は初唐になって整えられた。黄色は皇帝専用の色となり、皇帝は黄袍を着て、皇族と百官は紫・緋・緑・青色の袍服を位階により決められ、着ることを定められた。民の衣は、白や黒が基本であった。貴族や官僚の衣は絹が使われ、民は褐と呼ばれるズボン形式の麻の衣を着た。百官はまた位階により定められた冠や魚袋、笏をつけて朝廷に出仕した。
男性の服飾は、従来のゆったりとした服飾に代えて、胡服と呼ばれた北朝で流行していた北方民族の衣を源流とする衣が中心となった。頭には、?頭という頭巾が流行し、身分に関わらずつけていた。胡服は狭い袖の上着、ズボンで、革帯で締め、長靴で乗馬しやすいものであった。また、丸襟の袍衫が好まれ、布製に代わり、革の履が使用された。また、西域から来た胡服を着ていたという説もある。
女性の服飾は、胡服の流行や外国の服飾が導入され、国家に関係なく自由であり、色とりどりに染色したものが使われ、絶え間なく、移り変わっていった。大多数は、短い襦か長い衫をつけ、下半身に胸や腹まで引き上げる長裙をつける襦裙を着ていた。他に、襦裙の上半身の上に着る半臂という半袖の衣が好まれた。また、披帛という薄く軽い絹の布を肩にかける装飾品も使われ、先の尖った履をはいた。胸元まで露出することがあり、開放的なものであった。襦裙は時代がすすむとともに、ゆるやかなものに変わっていった。
宮廷の女性の間で女性が男装を行い、盛唐以降に民間で流行し、男性用であった服飾を女性が着ることが多くなった。別に流行ったものとして、胡服がある。これは男性のものとは違い、主に西域から入ってきたもので、狭い袖の上着、長ズボン、長靴が特徴的であった。
頭には、顔を見られぬために、冪リ(べきり、『リ』は「よんまがえ」と下部が「離」)と呼ばれる全身を覆う布がついた頭巾をつけた。次第に、帷帽というつばが広い、つばにつけた紗(うすぎぬ)を顔から首まで垂らした帽子をつけるようになった。胡服が流行してからは、西域から入ってきた胡帽が流行り、顔をうすぎぬで遮らなくなった。その後、渾脱帽という頭の先が尖った顔を出す帽子をつけるようになった。
女性の髪型は、多様なものになった。髻は、高髻をはじめとして、100種近くも存在した。まず、宮中の女性で流行り、民間に伝わった。髻には、様々な材質に細工が施された簪を頭につけ、10本以上もつけることもあった。
化粧は?脂が流行し、額や頬に塗られた。また、顔を飾るための額黄、黛眉、花鈿、斜紅などの工夫がなされ、額黄は額に黄色のパウダーを塗るもので黛眉で眉を描き、多様な眉の描き方が存在した。花鈿は、金箔、紙などを様々な模様に切り、額や頬を飾るもので、粧靨は両頬にえくぼを描くもの、斜紅は顔の両側で紅を斜めに描くものであった。装飾品は、耳飾り、頭飾り、ネックレス、腕輪、香袋などがつけられた。
女性と結婚
唐代は、儒教礼節による束縛が弱かったことと、北方民族の習慣による影響により、中国の歴史上で比較しても、女性の地位が例外的なほどに高かった。そのため、女性の精神面、肉体面における活動は開放的で活発であった。
盛唐時代には、女性は顔を露わにして馬に座るのではなく、またがった上で外出を行い、そのときに、積極的な様々な異国の服飾や男装を着ることが多かった。また、ポロなどの運動や狩りなども積極的に行っていた。また、男性と酒の席で同席して会話を交わし、単独で男性と交流し、友人となることもあった。
官僚の夫人たちは、家に閉じこもらずに、お互いに社交活動を行い、夫の公務を助けることもあった。また、官僚の家の女性たちは男性の客を避けるような傾向は強くはなかった。
政治においては、唐代前期に、武則天のように皇帝となるものもあらわれ、韋皇后、安楽公主、太平公主など政治に関わりを持つ女性が多数、輩出した。しかし、「女禍」と呼ばれ、中唐以降は政治に参画する女性はほとんどいなくなった。軍事においても、高祖の娘である平陽昭公主や皇帝を自称して鎮圧された陳碩真のような事例も存在し、行動的であった。
また、文化活動でも活躍し、多数の女性による唐詩が作られ、上官婉児・李季蘭・薛濤・魚玄機など著名な女流詩人も輩出した。歌舞や音楽において、宮廷や民間ともに女性が大きな役割を果たし、楊貴妃も名人であることで知られる。散楽における女芸人や書法において優れた技量をもった女性がいた。
また、当時の伝奇小説や唐詩によれば、多くの女性が自発的な愛情を持ち、それを世間に肯定的に受け止められ、時には親に許され、夫ですら強く責めないことがあったことが分かる。恋愛において、男性は才能を重んじられ、女性は容貌を重んじられた。
唐代は道徳からいえば推奨されていたとはいえ、婦徳に基づいた行動をした「列女伝」に名を連ねる女性の数は少なく、絶賛されるほどではなかった。庶民層には家事を行わず、礼節を守らない女性もあり、官僚にも恐妻家といわれる夫も多かった。姑と嫁の関係も、一方的に姑が強いものではなく、家庭内礼節は守られないことが多かった。未婚の女性が男性と交際し、処女ではなくなったり、富裕層の既婚女性が愛人を交わることもよく見られ、貞操観念は強くなかった。中唐以降は、儒教による礼節が厳しくなり、このような女性による行動の事例はあまり見られなくなった。また、徳宗時代に、宋氏の五姉妹によって、「女論語」が著される。「女論語」は読みやすく、夫に対する服従とともに、女性の家庭において果たす積極的な役割を説くという面も存在した。
女性の教育は、詩歌や書法、礼法、管弦などの音楽、裁縫と機織りなどに行われ、階層によって、重点が異なっていた。士族では7歳前後から書を勉強し、経典を読んだ。商人や武官、庶民の家でも書を知る女性は少なくはなかった。書を読むことにより、礼法を学ぶことに重きを置かれ、詩歌については士族の女性が身につけることは肯定されなかったため、礼法に緩い士族の家や、庶民や妓女の女性が勉学された。識字できる女性の層は全体的に広がっていた。音楽は、官僚や士族、一部の庶民の家では、広く学ばれ、楽器や歌を修得する女性が多かった。裁縫は多くの階層で学ばれ、庶民階級では裁縫と機織りが家庭教育の中心であった。女性の教育は、その母親が行った。
女性には様々な家事労働があり、その主要な役割を果たしていた。一般官吏や庶民の家では女性が家事や育児、料理を行ったが、最も主要な家事が針仕事であった。針仕事によって作られた布で衣服を自給し、兵役の男性に軍服を与え、税である布類を納め、生計を助けた。夫の仕事を手伝うこともあった。男子の幼少期や女子の教育も行い、父母舅姑や夫の世話もした。
結婚について、律では一夫一妻制をとっていたが、多妾は認められていた。良人と賤人の結婚は許されず、士族と庶民の差も厳格なものではなかったが、厳然として存在した。女性の婚期は13歳から18歳まで、大体15歳前後であった。結婚は親の命令で行われたが、親が娘に夫を選ぶことを許すこともあった。結婚において、男性は家柄・財産・文才が重視され、女性は容貌・家の財産が重んじられた。結婚は六礼を経る過程で、結納や持参金が必要であった。貧家の女性が婚姻できず、高齢の男性と若年の女性の婚姻がなされるという問題も生まれた。夫が妻の実家で婚礼を行い、妻が夫の実家に赴かず、夫が入り婿となることも多く、妻は家庭の中で比較的、高い位置にいた。結婚後も妻の実家である妻族が、妻の強い力となり、夫に圧力を与えることもあった。婚姻を行っているにもかかわらず、女性が夫以外の男性と自由な性愛関係が行われ、道徳的に強い批判がなされないこともあった。
上層階級の妻は、出産と育児、家政、裁縫・機織・料理などの家事、夫の業務や社交の補佐などが社会機能として求められ、妾には家政の代わりに、夫への快楽の提供などが要求された。上層階級の妻には、家全体を整え、夫の官界への評判と評価を高めることが期待された。夫の業務や社交の補佐については、多大な貢献が行われたことが多くの記録で分かる。
離婚や再婚の事例は多く、律によって、夫が妻と離婚してよい場合として、七出を犯した場合が定められている。七出には、男子を産まないことや、舅姑によく仕えないこと、嫉妬深いことなどがあげられており、男性は栄達して、妻を換えることがしばしば見られた。ただし、唐代の特徴として、夫婦における協議離婚や妻から積極的に離婚を要求することも、認められていた。また、女性の再婚もむしろ推奨されていた。皇帝の娘である公主は夫が死去した後、多くが再婚しており、特別なものではなかった。
唐代では、南北朝時代から続く、上層階級の妻が夫の女性関係への激しい嫉妬を示す妬婦の事例が多いのも特徴である。背景には、北方民族における母系制度の影響、礼節道徳が弱かったことと、多妾制度と正妻の立場が曖昧であったことがあると考えられる。嫉妬深いことは、夫が離縁する「七出」の一つにあげられているが、妬婦たちは夫へ激しい嫉妬を示し、夫に激しい怒りを露わにし、夫の寵愛する妾や婢を傷つけ、殺すなどの行為を行った。次第に、多妾制度が定着していったため、妬婦の勢いは弱まっていった。
律上では、女性の権利は男性に比べればかなりの制限があった。女性は財産の相続権を有さず、戸絶(家の後継ぎがいないこと)の時のみ、相続権が与えられた。妻が夫のもとを勝手に去った場合は罰せられ、夫婦の暴力は妻がおこした場合の方が重かった。また、戦乱の時には多くの女性が殺戮や略奪の対象となった。その一方で、母親は子に従うことを推奨されることはなく、敬い、孝行するべき対象とみなされていた。
たった一度の成り行きの情交のおよび、仮に嫁いだけれど、一生後悔する。女性の嫁ぎ先がなかったころの事である。
白居易はこの詩で、淫らな自由結婚をやめさせようとすることを主張している。
| 井底引銀瓶 止淫奔也。 作者:白居易《全唐詩/卷427》 文章還沒有進行過校對和格式化,或文章還不全,不能保證任何部分可靠。 |
(井底 銀瓶を引く。)淫奔を止むる也。 |
| 井底引銀瓶,銀瓶欲上絲繩?。 | 井底 銀瓶を引く,銀瓶 上らんと欲して 絲繩 ?つ。 |
| 石上磨玉簪,玉簪欲成中央折。 | 石上 玉簪を磨く,玉簪 成らんと欲して 中央より 折る。 |
| 瓶?簪折知奈何?似妾今朝與君別。 | 瓶?み 簪折る 知らず奈何せん?妾が今朝 君と別るるに似たり。 |
| 憶昔在家為女時,人言舉動有殊姿。 | 憶う昔 家に在りて 女【むすめ】為りし時,人は言う 舉動 殊姿有りと。 |
| 嬋娟兩鬢秋?翼,宛轉雙蛾遠山色。 | 嬋娟たる兩鬢は 秋?の翼,宛轉たる雙蛾は 遠山の色。 |
| 笑隨戲伴後園中,此時與君未相識。 | 笑いて戲伴に隨うこと後園の中,此の時 君と未だ相い識らず。 |
| 妾弄青梅憑短牆,君騎白馬傍垂楊。 | 妾は青梅を弄んで 短牆に憑り,君は白馬に騎って 垂楊に傍【そ】う。 |
| 牆頭馬上遙相顧,一見知君即斷腸。 | 牆頭 馬上 遙かに相い顧りみる,一見 君が即ち腸を斷つを知る。 |
| 知君断腸共君語、君指南山松柏樹。 | 君が腸を斷つを知って 君と共に語り,君は指さす 南山の松柏樹。 |
| 感君松栢化為心、暗合双鬢逐君去。 | 君が松柏を化して 心と為すに感じ,闇に雙鬟を合して 君を逐うて去る。 |
| 到君家舍五六年,君家大人頻有言。 | 君が家に到りて 舍【お】ること五、六年,君が家の大人 頻りに言有り。 |
| 聘則為妻奔是妾,不堪主祀奉蘋?。 | 聘【へい】すれば則ち妻為り奔れな是れ妾,祀りを主【つかさ】どり蘋?奉に堪えずと。 |
| 終知君家不可住,其奈出門無去處。 | 終【つい】に知君が家に住するべからず,其れ門を出れば去處無きを奈【いかん】せん。 |
| 豈無父母在高堂?亦有親情滿故?。 | 豈に父母の高堂に在る無からんや?亦た親情の故?に滿つる有り。 |
| 潛來更不通消息,今日悲羞歸不得。 | 潛かに來たりてより更に消息を通ぜず,今日 悲羞すれども歸り得ず。 |
| 為君一日恩,誤妾百年身。 | 君が一日の恩の為に,妾が百年の身を誤る。 |
| 寄言癡小人家女,慎勿將身輕許人! | 言を寄す 癡小なる人家の女,慎しみて身を將って輕しく人に許すこと勿れ! |
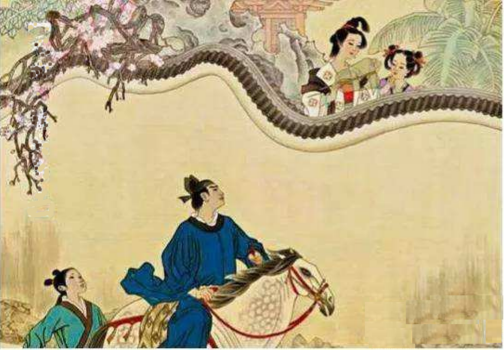 |
|